オーストラリア海軍 次期フリゲート艦 選定は? 日本の『もがみ型』が最終候補に残る?(次期フリゲート艦、もがみ型、日豪連携)豪州次期フリゲート艦計画:日本『もがみ型』とドイツ『MEKO A-200』が最終候補に
日本版「もがみ型」護衛艦、オーストラリア海軍フリゲート艦共同開発の最終候補に! 過去の失敗を教訓に、官民一体で技術力と外交力を結集し、豪州とのシーレーン防衛強化を目指す。アジア版NATO構想実現にも繋がるか? 豪州が求める国内建造への対応が鍵。日本防衛産業の未来をかけた、歴史的挑戦が始まる!
共同開発の具体性とメリット
豪政府、次期艦艇の共同開発先はどこ?日本も目指せる?
来春選定、日本も立候補。もがみ型が有力。
第三章では、共同開発の具体的な内容と、そのメリットについて詳しく見ていきましょう。
公開日:2024/05/07

✅ 日本政府はオーストラリアの汎用フリゲート導入に向けて、三菱重工業などと共同開発を検討しており、豪政府の要求に応じたもがみ型ベースの艦艇開発を視野に入れている。
✅ 豪州は海軍再編の一環として汎用フリゲートの取得を計画しており、日本、スペイン、韓国、ドイツの艦艇が候補に挙がっている。年内にも具体的な要求性能が示される見込み。
✅ 日本が受注競争を勝ち抜くためには、海外での防衛事業経験やプロジェクト管理能力を持つ企業との連携が重要となる可能性がある。他国も受注に向けて動きを見せており、競争は激化する見通し。
さらに読む ⇒航空万能論GF出典/画像元: https://grandfleet.info/japan-related/japan-also-participates-in-frigate-procurement-for-the-australian-navy-considering-development-of-vessels-based-on-mogami-class/もがみ型は少人数運用と機雷除去能力が特徴とのこと。
豪政府の要望に合致し、受注に繋がることを期待しています。
オーストラリア政府は来春に共同開発先を選定予定であり、自民党国防部会からは「ディスカウントしてでも取りに行くべき」との声が上がっています。
防衛省は三菱重工業などと非公式協議を開始し、豪政府の要求性能を踏まえて検討を本格化させる方針です。
「もがみ型」は少人数運用と機雷除去能力が特徴で、豪政府が重視する汎用性にも合致すると見られています。
日豪で艦艇を共通化することで、相互運用性と抑止力の向上、国内防衛産業への経済効果も期待されます。
ディスカウントしてでも取りに行くべき、ですか。本当に重要なのでしょう。頑張って欲しいですね!
競争激化と安全保障上の背景
豪州次期艦艇を受注するのは?日本は勝てる?
受注競争激化!日本は潜水艦の轍を踏むか?
第四章では、競争の激化と、安全保障上の背景について詳しく見ていきます。
公開日:2024/11/08

✅ オーストラリアの次期フリゲート艦建造計画で、日本とドイツが最終候補に残っており、日本の「もがみ型」とドイツの「MEKO A-200」が競合している。
✅ 「もがみ型」は、垂直発射システムによる多様なミサイル運用能力や、オーストラリアが運用する武器システムとの互換性が評価されている一方、日本には戦艦の輸出実績の少なさや価格競争力に課題がある。
✅ 最終選考は来年行われ、2029年に最初の艦が引き渡される見通し。日本が選ばれれば、既存の米豪連携に加え、安全保障上のパートナーシップを拡大する機会となる。
さらに読む ⇒NewSphere - 世界と繋がるミレニアル世代に向けて、国際的な視点・価値観・知性を届けるメディアです。出典/画像元: https://newsphere.jp/world-report/20241108-1/日独の競争は激しいですが、日本の技術力と、豪州との安全保障上の関係を考えると、十分勝機はあるのではないでしょうか。
オーストラリア政府が新型艦艇11隻を導入する計画を発表し、日本、スペイン、韓国、ドイツの4か国に共同開発を提案する見込みです。
2024年11月には、豪州政府は、次期フリゲート艦の候補としてドイツの「MEKOA-200型」と日本の「もがみ型」護衛艦の能力向上型を選定しました。
防衛装備移転三原則に基づき、国際共同開発相手国への輸出は認められており、今回の案件もその範疇に入ります。
日本政府はライバル国の動向にも注視し、受注競争に臨む構えです。
しかし、過去の潜水艦共同開発での受注失敗や、スペインや韓国の豊富な実績が競争を激化させると予想されます。
オーストラリアは米英との安全保障枠組み「AUKUS」を通じて原子力潜水艦の配備を計画しており、これに伴い水上戦力の再編を進めています。
AUKUSとの連携も踏まえると、オーストラリアの安全保障戦略における日本の重要性は増していると言えますね。頑張ってほしいですね。
今後の展望と課題
日本の防衛装備輸出、オーストラリアとの関係で何が焦点?
国内建造と防衛三原則への合致が課題。
最終章では、今後の展望と課題について解説します。
公開日:2024/11/28
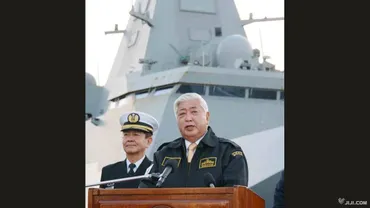
✅ 政府は、オーストラリア海軍の新型フリゲート艦建造計画で海上自衛隊の「もがみ」型護衛艦が採用された場合に備え、海外移転を認める手続きを行った。
✅ これは、防衛装備移転三原則とその運用指針に沿った措置であり、豪政府は「もがみ」型とドイツのフリゲート艦のどちらかを選定する予定である。
✅ 国家安全保障会議(NSC)は、豪州との共同開発・生産が日本の安全保障上高い意義を有し、問題はないと判断しており、「もがみ」型は三菱重工業が建造し、少人数で運用できる点が特徴である。
さらに読む ⇒時事ドットコム:時事通信社が運営するニュースサイト出典/画像元: https://www.jiji.com/jc/article?k=2024112801149&g=pol過去の教訓を活かし、官民一体で取り組むことが重要ですね。
日本が受注し、安全保障分野で貢献できることを願っています。
日本は、防衛装備品の海外移転を活発化させており、ウクライナ侵攻を契機に浮き彫りになった日本の継戦能力の問題と、防衛産業の維持・強化の必要性に対応しています。
「もがみ」型は全長133メートルとコンパクトで、約90人で運用できるのが特徴です。
日本が受注するには、防衛装備移転三原則に合致することに加え、オーストラリアが求める国内での建造(8隻)に対応できるかが課題となります。
日本政府を最大限サポートし、日本とオーストラリアが安全保障分野で先陣を切ることが、歴史的な一歩となると展望しています。
過去には、豪州の潜水艦建造計画で日本はフランスに敗れた経緯があり、今回のフリゲート艦の案件がどうなるか注目されています。
過去の潜水艦の件は残念でしたが、今回はぜひ良い結果を期待したいですね!
オーストラリアの次期フリゲート艦選定を巡る、日豪の取り組みについて解説しました。
日本が受注し、更なる安全保障上の連携が進むことを期待しています。
💡 オーストラリア海軍の次期フリゲート艦選定は、日本とドイツの2か国に絞られ、最終決定が迫っている。
💡 日本の『もがみ型』は、高い技術力と豪州との安全保障上の強固な関係を背景に、受注を目指している。
💡 日豪共同開発は、安全保障強化、経済効果、技術交流など、両国にとって多くのメリットがある。


