国際プラスチック条約とは?プラスチック汚染問題への取り組みと企業の役割、今後の課題について解説?プラスチック汚染問題に対する国際的な取り組みの現状と課題
世界を揺るがすプラスチック汚染問題。国際プラスチック条約の行方を追う!G7から始まった取り組みは、法的拘束力のある条約へと発展。170カ国が参加する交渉の舞台裏では、規制範囲や化学物質問題で意見が対立。自動車業界への影響も必見。持続可能な社会実現に向けた企業と社会の挑戦が始まる。
条約に期待される内容と企業の役割
企業は何をすべき?国際プラスチック条約で変わること?
プラスチック削減、リサイクル、環境負荷低減。
WWFジャパンが中心となり、企業連合が発足しました。
プラスチック削減、循環、予防・軽減を柱としたルールを求めており、日本政府への働きかけも行っています。

✅ WWFジャパンは、プラスチック汚染対策の国際条約の制定を推進するため、「国際プラスチック条約 企業連合(日本)」を発足し、日本政府に対し野心的な国際条約の発足を求める共同声明を発表しました。
✅ 企業連合には、Uber Eats Japan、エコリカ、キリンホールディングス、サラヤ、テラサイクルジャパン、日本コカ・コーラ、ネスレ日本、ユニ・チャーム、ユニリーバ・ジャパン、ロッテなど10社が参画し、WWFジャパンが事務局を務めます。
✅ 企業連合は、プラスチックの削減、循環、予防・軽減を柱とした、法的拘束力のある世界共通ルールに基づく条約を求めており、11月にケニアで開催される国際条約の政府間交渉(INC-3)に向けて、日本政府への働きかけを行います。
さらに読む ⇒PR TIMES|プレスリリース・ニュースリリースNo.1配信サービス出典/画像元: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000209.000018383.html企業が積極的に関与しているのは心強いですね。
持続可能な社会の実現のため、企業が果たす役割は非常に大きいです。
今後の動向に注目したいと思います。
国際プラスチック条約には、法的拘束力のある規制の導入、全ライフサイクル規制、プラスチック汚染による人の健康への影響防止、企業の積極的な関与、リサイクルの促進などが期待されています。
企業は、プラスチックの削減、リサイクル、再利用の促進、環境中への漏出防止に向けて、積極的に取り組むことが求められます。
具体的には、プラスチックの生産・設計段階での規制に対応し、有害物質の使用を制限すること、リサイクル可能な製品のデザインを開発することなどが重要になります。
エレン・マッカーサー財団やWWFが呼びかけ、150以上の企業、金融機関、NGOが参加する国際プラスチック条約企業連合も設立され、条約を支持しています。
日本では、WWFジャパン事務局のもと10社が立ち上げ企業として参画しています。
企業が今後取り組むべき課題としては、プラスチックのライフサイクル全体における環境負荷低減、労働者や消費者の安全確保、製品情報の透明性確保などが挙げられます。
特に、原料調達段階における環境への配慮が重要になります。
企業が積極的に取り組む姿勢は素晴らしいですね!環境問題は、企業だけでなく、私たち一人ひとりの意識も大切だと思います。
自動車業界への影響と対応
自動車業界に迫る!国際プラスチック条約の影響とは?
持続可能な製品設計と廃棄物管理の義務化。
国際プラスチック条約は、自動車業界にも大きな影響を与える可能性があります。
EUの規制強化や、リサイクル技術の進展など、対応が求められています。

✅ 国際プラスチック条約の策定に向け、世界170カ国以上が参加し、2040年までのプラスチック汚染解決を目指して法的拘束力のある国際条約の策定が進められている。
✅ 欧州では循環型経済行動計画に基づき、自動車業界に関連するELV規則やSUP指令などの規制が強化されており、日本でも自動車工業会が再生プラスチックの利用目標を掲げているが、EUの規則に比べると目標達成には追加の取り組みが必要となる可能性がある。
✅ 国際プラスチック条約は、法的な拘束力を持つ可能性があり、ビジネスへの影響も考慮され、特にEU市場の動向に注意が必要。リサイクル技術の進展も重要であり、サーマルリサイクル、ケミカルリサイクル、マテリアルリサイクルの3つの方法がある。
さらに読む ⇒NAGASE Business Websites出典/画像元: https://division.nagase.co.jp/mobilitysolutions/columns/PlasticRecycling/自動車業界も対応を迫られているんですね。
リサイクル技術の進歩は、持続可能な社会の実現に不可欠です。
今後の技術革新にも期待したいですね。
国際プラスチック条約の策定は、自動車業界にも大きな影響を与える可能性があります。
条約により、持続可能な製品設計や廃棄物管理に関する行動計画が各国に義務付けられる見込みです。
欧州では、循環型経済への移行を目指す「新たな欧州循環型経済行動計画」が発表され、ELV規則やSUP指令など、プラスチックに関する法規制が強化されています。
日本では、日本自動車工業会が2030年までに廃車由来プラスチックを年間2.1万トン使用する目標を掲げていますが、EUの規則案が求める水準には達していない可能性があります。
自動車業界は、リサイクル技術を活用し、サーマルリサイクル、ケミカルリサイクル、マテリアルリサイクルなど、様々な技術を駆使して、持続可能な社会の実現に貢献していくことが求められています。
自動車業界も大変ですね。でも、自分たちが乗る車が環境に配慮されているのは、私たちにとっても嬉しいことです!
今後の展望と課題
プラスチック条約、2024年末までに締結なるか?
INC交渉次第。注目が集まる。
国際プラスチック条約は、2024年までの国際的なプラスチック規制の枠組み構築を目指しています。
今後の交渉の行方、そして条約がもたらす影響に注目です。
公開日:2024/11/01
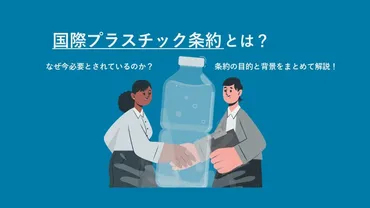
✅ 国際プラスチック条約は、2024年までに国際的なプラスチック規制の枠組みを構築することを目指し、プラスチックの全ライフサイクルを対象とした法的拘束力のある規制を設けることを目指している。
✅ 条約の実現に向けて、約170か国の国連加盟国などが参加する政府間交渉委員会(INC)が開催され、企業連合も発足し、プラスチック削減への企業の積極的なコミットメントや、再利用・リサイクルを促進するプロダクトデザインの開発などが期待されている。
✅ 条約ではプラスチックによる人の健康への影響も考慮される一方で、プラスチック汚染の影響を最も受けている人々への言及が不十分であることや、回収・分別・リサイクルに携わる人々への経済的影響への配慮が必要と指摘されている。
さらに読む ⇒株式会社エスプールブルードットグリーン出典/画像元: https://www.bluedotgreen.co.jp/column/esg/plastics-treaty/今後の交渉の進展が重要ですね。
条約の締結だけでなく、その後の効果測定や、継続的な改善も必要になるでしょう。
国際プラスチック条約は、プラスチック汚染問題に対する国際的な協調を強化し、持続可能な社会の実現に貢献することが期待されています。
しかし、条約の具体的な内容や効果は、今後のINCでの交渉の進展に大きく左右されます。
今後は、条約の対象範囲、プラスチック製品に含まれる化学物質の問題、途上国への支援など、様々な論点について、更なる議論が必要となります。
INC5.2での交渉を踏まえ、2024年末までに条約が締結されるのかどうかに注目が集まっています。
プラスチック汚染問題の解決に向けたグローバルな取り組みは、今後も継続的に行われていくでしょう。
プラスチック問題は、私たちの子どもたちの世代にも影響がある問題なので、しっかりと対策してほしいですね!
本日は、国際プラスチック条約について解説しました。
プラスチック汚染問題の解決に向けて、今後の動向を注視していきましょう。
💡 国際的なプラスチック汚染問題に対処するため、法的拘束力のある国際条約の策定が進められている。
💡 条約の対象範囲や、プラスチック製品に含まれる化学物質の問題など、解決すべき課題は多い。
💡 企業連合が発足し、プラスチック削減、循環、予防・軽減を柱としたルールを求めている。


