難民問題とは?世界と日本の現状、私たちができること(多文化共生、UNHCR、入管法)?世界で増え続ける難民と、日本の現状、私たちにできること
世界で67人に1人が難民という深刻な現実。迫害から逃れる人々を日本はどのように受け入れているのか?低い難民認定率の背景にある日本の独自解釈、手続きの課題、そして国民の関心の低さとは?国際社会の一員として、私たちができること、難民支援団体の活動、そして多文化共生社会の実現に向けた取り組みを解説します。
日本の難民認定制度の課題
日本の難民認定率が低い原因は?制度の問題?
難民条約の解釈、手続き、入管の実務など。
日本の入管法は、難民申請者などの収容に関する問題も抱えています。
長期収容や、人権侵害の可能性が指摘されており、国際社会からも改善を求められています。
公開日:2025/02/17
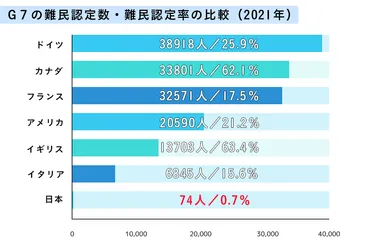
✅ 2021年の入管法政府案は、難民申請者などの人々を収容する際の条件や手続きの見直しを目的としていましたが、国際社会からの批判や、収容の実態が本来の目的と異なっていることなどが問題視され、事実上の廃案となりました。
✅ 入管施設での収容は、送還までの準備として行われるべきものですが、実際には、帰国を促す手段として利用されたり、長期間にわたる収容によって死亡するケースも発生しており、人権侵害との批判を受けています。
✅ 国際社会からは、日本の入管収容体制に対し、期間制限や司法による判断の導入を求める声が上がっています。また、退去強制令を受けた者の多くが送還に応じていることや、犯罪歴が理由で強制退去となるケースは少ないことも指摘されています。
さらに読む ⇒Dialogue for PeopleのWEBサイト - トップページ - Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル)出典/画像元: https://d4p.world/19702/入管施設での長期収容や、人権侵害の可能性が指摘されているという点は、非常に深刻な問題です。
難民の方々が安心して生活できる環境を整えるために、制度の見直しが必要だと思います。
日本の難民認定率が低い原因は、制度的な課題に起因しています。
具体的には、難民条約の解釈における日本の独自性、迫害の定義の厳格な解釈、そして申請手続きにおける課題が挙げられます。
これらの問題は、難民申請者にとって公正な手続きが担保されていない可能性を示唆しており、国際的な基準との乖離を生んでいます。
さらに、入国管理局(入管)による難民申請の実務が、難民保護という本来の目的にそぐわない側面があることも、課題の一つです。
入管施設における長期収容の問題も深刻で、身体的、精神的な負担が長期化する可能性があります。
ウィシュマ・サンダマリさんの死亡事件は、この問題の深刻さを浮き彫りにしました。
入管施設での長期収容は、まるで刑務所のようですね。難民の方々の置かれている状況を考えると、もっと人道的な対応が必要だと思います。旅行中、色々な国の入管を見ましたが、日本の入管は改善の余地があると感じます。
日本ができること:難民支援の様々な形
難民支援、日本は何してる?手軽な支援方法は?
寄付、ボランティアなど、様々な形で支援可能。
DNPは、国連UNHCR協会に寄付を行い、社員食堂での応援メニュー提供など、長期的な支援活動を展開しています。
また、募金活動なども実施し、全社員が難民支援に参加できる企画を推進しています。

✅ DNPは、国連UNHCR協会に5年間で計5千万円を寄付し、難民救援活動を支援します。
✅ 社員食堂での「応援メニュー」の提供を通じて、難民支援団体への寄付など、長期的な支援活動を展開します。
✅ 「世界難民の日」や「人権月間」などの機会に、募金活動などを実施し、全社員が難民支援に参加できる企画を推進します。
さらに読む ⇒DNP 大日本印刷株式会社出典/画像元: https://www.dnp.co.jp/news/detail/10162698_1587.html企業による難民支援の取り組みは、非常に素晴らしいですね。
寄付やボランティア活動、情報発信など、様々な形で難民を支援できるということも、改めて認識しました。
日本は、国際社会の一員として、難民支援のために様々な取り組みを行っています。
政府は、UNHCRなどの国際機関を通じて、シリア難民の受け入れ支援や、その他の地域への人道支援を行っています。
また、難民認定制度を導入し、難民の受け入れと支援にも力を入れています。
個人レベルでも、さまざまな形で難民を支援することが可能です。
寄付、衣類や書籍の寄付、ボランティア活動、支援団体やイベントへの参加、そして難民問題への理解を深め発信することなどが挙げられます。
難民支援協会、WELgee、AAR Japan、ワールド・ビジョン・ジャパン、ユニセフなど、日本国内で活動する様々な支援団体への寄付は、手軽に始められる支援方法の一つです。
これらの団体は、難民の就労支援、食料支援、教育機会の提供など、多岐にわたる活動を行っており、寄付を通じてこれらの活動を支えることができます。
企業が積極的に支援活動を行っているのは素晴らしいですね。僕も旅行先で、現地のNPOに寄付したりすることがあります。難民支援団体への寄付も、手軽にできる支援の一つですね。旅先での出会いを大切にしたいです。
難民問題への理解と多文化共生社会の実現
難民問題解決に不可欠なことって何?
理解と行動、多文化共生社会の実現!
近年、外国人児童生徒が増加し、学校教育における多文化共生のあり方が課題となっています。
文部科学省は日本語教育や共生社会の理解促進のための施策を展開しています。

✅ 近年、外国人児童生徒が増加し、学校教育における多文化共生のあり方が課題となっており、文部科学省は日本語教育や共生社会の理解促進のための施策を展開している。
✅ 外国人児童生徒の増加に伴い、日本語指導が必要な児童生徒も増加しており、特に義務教育段階では指導体制の確保や指導力の向上が課題となっている。
✅ 文部科学省は、外国人児童生徒の就学促進、指導体制の充実、日本語指導担当教師の指導力向上など、様々な施策を実施している。
さらに読む ⇒日本文教出版|小学校・中学校・高校の教科書/デジタル教科書・教材出典/画像元: https://www.nichibun-g.co.jp/data/web-magazine/manabito/inclusive/inclusive046/多文化共生社会の実現に向けて、教育の現場での取り組みが重要であるということが分かりました。
難民の方々だけでなく、様々なバックグラウンドを持つ人々が共に生きる社会を築くために、教育の役割は大きいと思います。
難民問題は、国際社会全体で取り組むべき課題であり、一人ひとりの理解と行動が重要です。
難民問題への関心を高め、多文化共生社会の実現に向けて取り組むことが求められています。
日本でも、国際基準を反映した柔軟な難民認定基準の導入や、手続きの透明性と効率性の向上が進められています。
企業による外国人採用の支援や、異文化理解を促進する情報発信も重要です。
難民支援を通じて、多様性と包容性のある社会を築き、難民の方々が安心して生活できる環境を共に作っていくことが大切です。
多文化共生って、すごく大事だと思います。色々な文化に触れることで、自分の価値観も広がりますよね。子供たちが色々なバックグラウンドを持つ友達と仲良くできる環境を作るのは、大人の責任だと思います。
この記事を通して、難民問題の深刻さを改めて認識しました。
私たち一人ひとりが、できることから始めて、多文化共生社会の実現に向けて取り組んでいくことが大切です。
💡 世界では、紛争や迫害により故郷を追われる人が増加し、難民問題は深刻化している。
💡 日本では、難民認定基準の厳格化や手続きの問題など、課題が残っている。
💡 難民支援には、寄付やボランティア、情報発信など、様々な形で参加できる。


